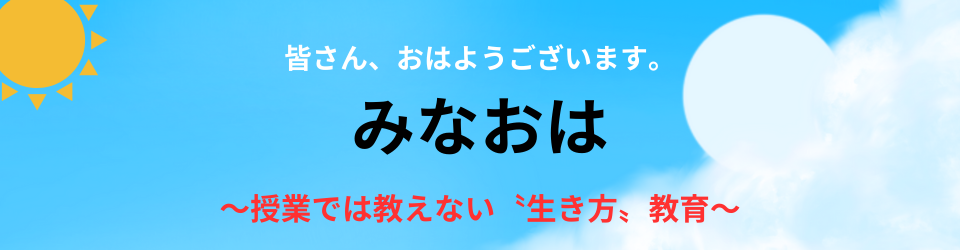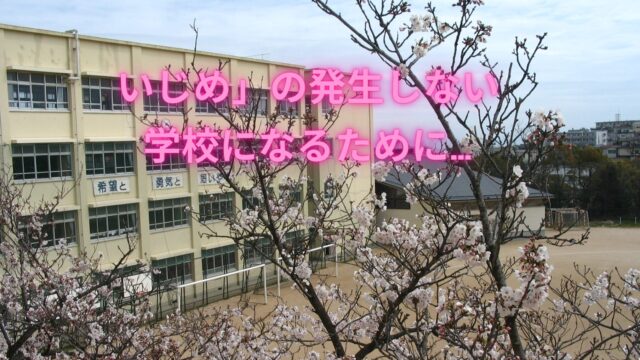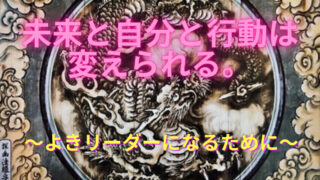「一年の計は元旦にあり。」

皆さん、あけましておめでとうございます。

2026年(令和8年) 午年
 |
価格:7312円 |
![]()
天下和順
浄土宗では、年始のお正月に「修正会(しゅしょうえ)」、もしくは「修正月会(しゅしょうがつえ)」という法要を行います。大晦日の除夜の鐘で前年を反省して悪を正し、煩悩を除いた清らかな身で新年を迎え、新たに天下安泰・五穀豊穣・心身の健康を祈願するものです。
その修正会でよまれる『無量寿経』というお経の一節に『祝聖文(しゅくしょうもん)』というのがあります。慶事に用いられるお経で、一年の無事を祈願します。
天下和順 てんげわじゅん 仏の教えによって天下が太平であり、
日月清明 にちがつしょうみょう 太陽も月も清く明らかに照らし、
風雨以時 ふうういじ 風や雨は時にかなって程よく恵みをもたらし、
災厲不起 さいれいふき 災害や疫病は起こらず、
国豊民安 こくぶみんあん 国家は豊かで民は安らぎ豊かになって、
兵戈無用 ひょうがむゆう 戦争の武器は用いることなく、
崇徳興仁 しゅうとくこうにん 人々は互いに仁を尊び、
務修礼讓 むしゅらいじょう 礼儀と謙譲の道を守る。

「そ・わ・か」と「う・た・し」の法則
3学期のスタート、誰もが今年はいい年にしたいと思っていると思いますが、毎日を「嬉しい!」「楽しい!」「幸せ!」と言える日にしたいものですね。
ところで、般若心経やいろいろなお経を見ると、一番最後が「薩婆訶(そわか)」という言葉で締めくくられているものがたくさんあります。潜在能力研究家の小林 正観氏が、「宇宙を味方にする方程式」という本で、「そ・わ・かの法則」というのを唱えています。
「そ・わ・か」というのは、「掃除」・「笑い」・「感謝」のことで、すべての悩みは、「そ・わ・か」で解決すると言っています。
◎「掃除」でお金と仕事の問題が片づきます。
◎「笑い」によって免疫力を高まり、健康になれます。
◎「ありがとう」の感謝の心から生まれる温かい会話によって、人間関係の問題は終わります
「そ・わ・かの法則」を実践することによって、「嬉しい」・「楽しい」・「幸せ」という「う・た・し」の状態になることができるのだそうです。
「夢の架け橋」
「一富士二鷹三なすび」

1月2日の夜から3日の朝にかけて見る初夢で良い夢とされているものですが、皆さんは何か初夢をみましたか。
「一富士二鷹三なすび」は、徳川家康の故郷、駿河の3つの名物だという説があります。ちなみに、宝船や七福神を描いた紙を枕の下に入れると良い夢がみられるそうです。
さて、本州と淡路島をつなぐ明石海峡大橋。
60年近くも前、土木工学の専門家でもあった当時の原口神戸市長は、明石海峡と淡路島そして鳴門に橋を架け、本土と四国を陸続きにしようと考えていました。そこで調査費の予算を市議会に出しました。すると、「財源に余裕がない」「市長は白日夢でも見ているのではないか」などと反対意見が出ました。この時、原口市長は、「人生は、すべからく夢なくてはかないません。」と言われたのだそうです。そして、その時以来、明石海峡大橋は「夢の架け橋」と呼ばれるようになりました。
原口市長はねばり強く橋の実現に向けて努力を続けました。残念ながら完成した姿を見ずに亡くなられましたが、原口市長の「人生は、すべからく夢なくてはかないません。」と言われた前向きな生き方は学ばなければならないと思います。

「夢あるところに」
夢あるところに計画あり。
計画あるところに実践あり。
実践あるところに向上あり。
向上は人間の悦びであり。
悦びは満足なり。
雑巾だってめでたし
澤木興道全集第二巻に、こんな話が載っています。
ある人が正月に神棚を拝んでいると、昨日大掃除した時に使った雑巾を見つけました。「正月草々、雑巾を掴むとは縁起が悪い。」と真っ青になっていると、近所の手合いがやってきて、
「雑巾を当て字に書けば、蔵と金。あちら福福(拭く拭く)、こちら福福」と歌いました。 一転して機嫌をよくし、大いに酒を振る舞ったそうです。
京セラの創業者で日航を立て直した稲盛 和夫氏は中村天風の「信念で寝て、信念で起き、信念 で一日中を生きよ。」という教えを地で行い、数々の奇跡を起こされた人でしたが、彼は、人生の結果を、
「人生の結果=考え方×熱意×能力」
という式で示しており、この中で最も重要な要素は、「考え方」だと述べています。同じ物事でも、プラス思考をするのか、マイナス思考をするのかで、大きく差が出てくるでしょう。
口に出す言葉
田口 久人(You Tuber:yumekanau2)「そのままでいい 」より
「たのしい」「うれしい」「おもしろい」「しあわせ」
いつも口に出して言っていれば、
人生はもっと楽しくなり、
もっと嬉しくなり、
もっと面白くなり、
幸せは続いていく。
「ゆっくり急げ」
「ゆっくり急げ」は、ローマ帝国初代の皇帝、オクタヴィアヌスの残した言葉だと言われています。

オクタヴィアヌスは、英雄シーザーの部下であったアントニウスとエジプト女王クレオパトラの連合艦隊をアクチウムの海戦で破り、その後、ローマに戻ってアウグスツスの称号を受け、帝政を築きあげます。彼の偉大だったところは、決して自分の私利私欲のためではなく、常に人々のために尽力を惜しまなかったことでしょう。この時代は、大変、平和な時代となりました。アウグスツスは、文学や美術を盛んにしたり、土木工事を起こしたりして、立派な建築物をたくさん建てました。こうして、ローマ文化の黄金時代を迎えるわけです。
文化の栄える国は、平和な国です。日本の歴史を振り返ってみても、平和な時代には文化が栄えています。
この「ゆっくり急げ」をモットーとしているのが、大阪の伊藤塾です。塾長の紹介文から・・・
| 司法試験は1年で受かる人もいれば、10年かかって受かる人もいる。だが1年で合格した人が偉くて、10年かかった人が劣るのかというと、けっしてそんなことはない。 10年かかった人でないと見られない景色がある。鈍行列車の窓から見る景色と、新幹線から見る眺めはまったく違うのだ。東京、新大阪間を3時間弱で走り抜ける爽快感もあれば、一つひとつ駅に止まっていくからこそ学べる情報や喜びもある。どちらがいいとか、素晴らしいという問題ではない。目的が何かによって違ってくるだけの話である。 ローカル線で旅情を楽しむ旅なら鈍行列車のほうがいいだろう。速く移動したいなら新幹線のほうがいいに決まっている。自分の人生の本当の目的は何なのか。自分は何をしたいのか。 前のめりに先を急ぐだけでなく、ときには立ち止まって、じっくり人生の意味や目的を考えてみるのもいいだろう。それでもなお、多くの人は新幹線に乗りたがる。その方が早く目的地に着くような気がするからだ。でも、本当にそうだろうか。 司法試験に特急で合格しても、鈍行で合格した人より幸せな人生を送れるかどうかはわからない。もしかしたら、10年かけて鈍行列車でやってきた人のほうが、苦しかった経験を糧に法律家として活躍できるかもしれない。どちらが幸せかは誰にもわからない。その人にとっていちばんいいときに合格するものなのだ。 だからゆっくり、一歩ずつ、時間がかかっても前に進め。そうすれば、必ずゴールに到着できる。たとえ自分が鈍行列車でも、あきらめるな、と私は言いたいのだ。 本当にダメだ、もうあきらめようと思った時が、実は一番ゴールに近いのだ。あきらめてはいけない。 そして一駅、一駅あきらめずに進んでいく力、忍耐する力、続ける力は勉強によって養われる。 あと1問、頑張って解く。あと1ページ頑張って読む。日々の勉強の積み重ねが、最後まであきらめない「根っこの忍耐力」を養ってくれる。勉強によって、あきらめない力を身につけることができるのである。 最後に私の座右の銘を贈ろう。・・・「やればできる、必ずできる!」 |
3学期は、学校・学年・学級のまとめに入ります。これまで築き上げてきた文化をまとめ上げ、来学年への種蒔きをして終わりたいところです。
「1月はいく,2月は逃げる,3月は去る。」というように、3学期はあっという間に終わってしまいます。ゆっくり急いで、3学期を締め括りましょう。
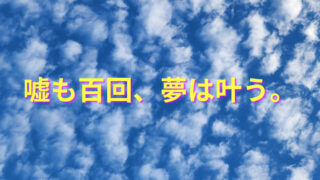
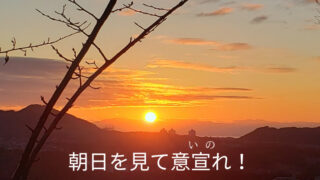
 |
「皆さん、おはようございます」授業では教えない“生き方”教育 スライドで語る全校朝礼のお話/長井功【3000円以上送料無料】 価格:1280円 |
![]()
 |
「皆さん、おはようございます」授業では教えない“生き方”教育 スライドで語る全校朝礼のお話【電子書籍】[ 長井功 ] 価格:1000円 |
![]()
 |
【送料無料】〔予約〕「皆さん、こんにちは」パワースポットが語ってくれた“人生の生き方”/長井功 価格:1540円 |
![]()
まとめ
「一年の計は元旦にあり」「1月はいく,2月は逃げる,3月は去る」というように、3学期はあっという間に終わってしまいます。ゆっくり急いで、3学期を締め括りましょう。
「天下和順」「そ・わ・か」と「う・た・し」の法則について語ります。