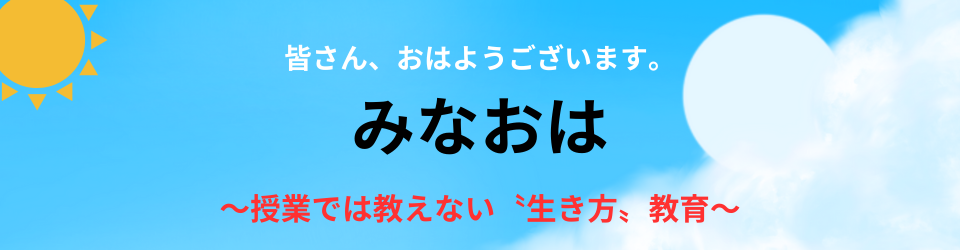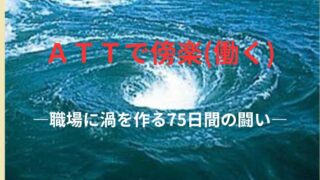「教育観」を変える海外研修
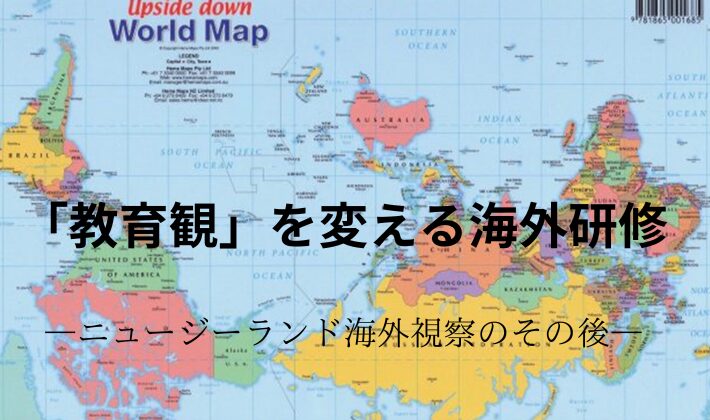
―ニュージーランド海外視察のその後―
私の海外研修体験
皆さん、おはようございます。
神戸市は、アメリカのシアトル市、フランスのマルセイユ市、ブラジルのリオ・デ・ジャネイロ市、中国の天津市、ラトビアのリガ市、オーストラリアのブリスベン市、スペインのバルセロナ市、韓国の仁川(インチョン)市と姉妹都市の提携を結んでおり、様々な交流を行っています。
残念なことに、最近はなぜか少なくなりましたが、教育界においても、生徒や職員の海外交流が頻繁に行われてきました。
私の体験だけでも、ラトビア(当時はソ連)のリガ市からバレーボールの教員チームが神戸に来て交流試合を行ったり、中国の天津市に行ってバレーボールの親善試合(実際は「親善」と言うレベルではなく、完全アウェイの中での大敗の試合でしたが・・・)をしたりしました。
また、アメリカのシアトル市から先生が来て学校訪問をされたり、オーストラリアのブリスベン市から生徒が来てホームステイしたりするなど、先生や生徒の交換事業もありました。
さらに、海外自主研修を計画・申請し、認可されれば、往復の費用を出してもらえるという制度があり、この制度を使って、アメリカのマサチューセッツ州ホーリヨーク市で行われた「バレーボール生誕百年祭」に参加し、バレーボール考案者のモルガン氏の孫娘さんと対面するいう体験もできました。
これらの交流会で、多くのことを学ばせていただき、その後、様々な教育活動に生かすことができたと思います。
ニュージーランド海外視察
極めつけは、文部科学省派遣の教員海外派遣研修で2週間、ニュージーランドに行った体験でした。
ニュージーランドのパンフレットに、「人生観の変わる国」という宣伝文句が書いてありましたが、私はニュージーランドへの教育視察で、「教育観」が大きく変わりました。
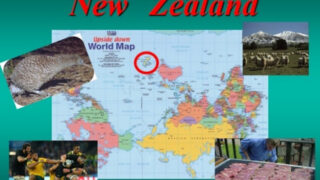
私は最初、「なんでこんな忙しい時期に、教育レベルの低い国に行かなきゃいけないんだ」などと思っていましたが、実際に行ってみると、ニュージーランドは日本よりはるかに教育レベルの高い国でした。
ニュージーランドには先住民族のマオリ族がいます。当初は争いが絶えなかったそうですが、ワイタンギ条約締結以降、友好的な関係が保たれています。そして、現在は、互いの言語・文化を大切にし、違いを認め、受け入れ合う共生社会が形成されていました。アングロサクソン系の白人と体格のいい先住民のマオリ族の人たちが、仲良く生活をしていました。
当時、アメリカでは高校生のよる銃乱射事件が頻発していました。私は、ニュージーランドの研修テーマに、Juvenile Delinquency(未成年者の法に反する反社会的犯罪行為)をあげて行ったのですが、治安のいいニュージーランドでは、青少年犯罪はほとんどありませんでした。
一番長く滞在した北島のネイピア市では、夕方になると、17時には全ての店が閉まり、川沿いの芝生の上を親子が仲良く散歩している姿を見かけました。こんなにいい環境の街で、青少年犯罪は似つかないと思いました。
共生教育を主軸に
ニュージーランド海外視察後、私は「共に生きる」という言葉を教育信条にし、教育実践を行うようになりました。そのいくつかを紹介しましょう。
1.スキー実習
生徒たちをスキーに連れて行くと、3日間でとても上手になります。
スキー実習を終えた時、ほとんどの生徒たちは、「スキーは楽しい!」と満足そうな表情で言います。
スキーが楽しかったかどうかは、天候やインストラクターの影響が大変大きいので、可能な限り、2月15日以降の春スキー日和の日に実施し、国際理解教育を兼ねてニュージーランド人の陽気なインストラクターを選びました。外国人インストラクターの方がSAJ(日本スキー連盟)のインストラクターより安く雇えるというメリットもありましたが、ニュージーランド人のインストラクターの多くは、お願いすると、夜の宿舎に来て「ハカ」を踊ってくれたりもしました。


2.修学旅行
昔の修学旅行のイメージは、観光バスに揺られ、観光都市に1~2泊して名所や旧跡を見学。夜は枕投げなどして大騒ぎ。そして、翌日のバスの中では、ガイドさんの説明を子守歌代わりに居眠り…。それでも、見知らぬ土地を訪れた感動が残り、思い出は残っているというようなものでした。
しかし、家族旅行等の機会が多くなってから、修学旅行のイメージは大きく変容してきました。体験学習や民泊を取り入れる学校も増えています。
生徒たちにとって一生に一度の修学旅行ですので、普段の学校生活や今後の人生の中でもあまり経験することのできない体験をさせてあげたいと思ってきました。
そこで、ニュージーランドで学んだ共生教育を元にして、現地の中学生と交流をすることをメインイベントにするようにしました。
(1)壱岐(K中学校)
長崎県の壱岐の民宿に2泊する修学旅行を計画しました。
この修学旅行に向けて、1年生の時から壱岐の石田中学校との学校交流をしました。お互いの学校行事をビデオレターにして交換をしてきました。
ちょうど、阪神・淡路大震災のあった平成7年5月の修学旅行であったこともあって、壱岐の島に到着した時、
「ようこそ壱岐へ。皆さん、お待ちしていました!」
と大きな横断幕を掲げて、島あげての歓迎を受けました。
石田中学校との交流会。石田中学校は3クラスの学年でしたが、合唱に圧倒され、腹話術を披露してくれたり、プレゼントのレベルの高さにびっくりさせられたりしました。グループ交流会で「毎日12時まで勉強している。」「昨日は1時まで勉強していた」という生徒たちの話にも驚かされました。その当時、壱岐には県立高校が1校しかなく、成績の振るわない生徒は長崎県本土の私立高校に行かなければならなかったのです。片道2時間のフェリーで通うわけにはいかず、私立高校に行くとなると親元離れての下宿となります。ですから、地元の県立高校に行くために、生徒たちは猛勉強していたのでした。K中学校の生徒たちはカルチャーショックを受け、帰ってきてから本当によく勉強するようになりました。
最後に島を離れる時、石田中学校の生徒たちがフェリー乗り場まで見送りに来てくれて、「きみに会えて」という歌を歌ってくれました。そして、何度も何度も、“See you again.”と言ってくれるのでした。
(2)松浦市(T中学校)
長崎県松浦市が、市をあげて修学旅行の誘致を始めました。「ほんなもん体験」と名をうって民泊を勧め、宿泊先の農家や漁師さんの家で農業・漁業・林業などの体験ができるというものでした。
そこで、松浦市の志佐中学校と3年間の学校交流を行い、民泊を計画しました。
生徒たちにとって、一生の思い出のひとつになったことと思います。
その当時、修学旅行実行委員になってくれた生徒たちは、卒業後10年以上もお互いに交流を続けています。隔年ごとに長崎と神戸で同窓会をしているそうです。

(3)沖縄(T中学校)
過去、世界の多くの地域で、ヨーロッパ諸国の侵略により、原住民は滅ぼされてきました。しかし、ニュージーランドでは、イギリスと原住民のマオリ族は「ワイタンギ条約」を締結し、共生社会を形成してきました。いじめのない平和な社会を構築するためには、戦争による解決法は絶対に避けなければなりません。
沖縄は、過去の歴史において、幾度となく、他民族に支配されてきました。また、第二次世界大戦において、民間人を直接巻き込んだ激しい現地戦が行われたところです。訪れるだけで、戦争や平和について考えざるを得ません。沖縄への修学旅行は一番の平和学習になるのです。
教育委員会から飛行機利用の許可が出たので、早速、私は一番に沖縄への修学旅行の計画を立て、生徒たちを連れて行きました。
当時、沖縄は「日本で一番荒れる成人式」ということで、ニュースにあがっていました。沖縄の中学校も荒れているということで、現地の中学校との交流はできませんでしたが、民泊をするなどして、沖縄の匂いを感じられる修学旅行を実施しました。
(4)奄美大島(A中学校)
ニュージーランドには、「キウイ」という飛ばない鳥や、今は絶滅してしまいましたが、つい最近まで街中でも2mの大きさにもおよぶ「モア」という鳥が見られるなど、独自の進化をとげた生物がたくさんいます。
鹿児島県の奄美大島も、「東洋のガラパゴス」と言われるように、独自の進化を遂げた固有種や希少種が多数存在しています。
また、奄美大島は台風の被害を多くうけるところでありながら、島民はたくましく生きているということや、田中 一村という独特の画家が移住されていたということもあって、多くの魅力を感じ、奄美大島への修学旅行を計画しました。
1年生の時から、奄美大島の赤木名中学校というところと学校交流を行い、3年生で初顔合わせをしました。
学校交流会で、赤木名中学校の生徒たちから奄美の文化をたくさん教えてもらいました。そして、薩摩酒造の芋焼酎「さつま白波」の2007年CM曲として使用された、中 孝介の「花」という曲を歌ってくれました。この歌を学年の歌とし、校内の文化祭や全市の連合音楽会で披露し、歌い続けました。

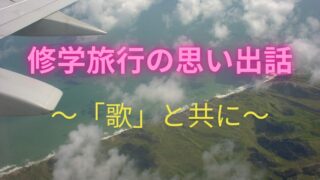
3.国際理解教育
現在、小中学校では、総合的な学習の時間などで、国際理解教育を行うことが必須となっています。ただ、なかなか計画的・組織的に実施されているわけでなく、実際に海外に行ったことのある先生が体験談を話すという授業がよくなされています。
私もよく依頼を受けてお話をしてきましたが、やはり、その際、生徒たちがその国にいいイメージを持って「将来、行ってみよう!」と思えるようにしなければならないと思います。
ところが、中には、その国や住んでいる人々のマイナス面を話される先生方がいます。「貧困だ」とか「犯罪が多い」とか、嫌な思いをしたなどと紹介された国を、誰が将来行こうと思うでしょうか?
私は様々な国に行ってきましたが、ニュージーランドの話をメインにするようにしています。なぜなら、一番いい体験をしたからです。ニュージーランドの話をした後、生徒たちにアンケートを取ると、ほぼ100%、将来行ってみたいと思ったと答えてくれています。
実際には行く機会がなかったとしても、ニュージーランドに感心を持ってくれるだけでいいのです。
2019年、新型コロナが世界的流行をした時、ニュージーランドは、国全体で厳格なロックダウンを実施し、市中感染者を完全にゼロにすることに成功し、その状態を102日間も維持できました。ニュージーランドに関心のある教え子たちは、そういう情報を生かすことができただろうと思います。
4.体育会マスゲーム 「A中ソーラン」
ニュージーランドのネイピア市の教育委員会との懇親会で、互いの文化を披露し合う機会がありました。
ニュージーランドのラグビーナショナルチームが試合前に「ハカ」という踊りを披露することがあります。これは、原住民マオリ族が戦闘の前に相手を威嚇するために踊った踊りでした。今ではニュージーランド人の殆どの人が踊れるそうです。
当然、懇親会でも「ハカ」を披露されるだろうと予想されたので、私たちも日本の踊りがいいだろうということで、事前に打ち合わせをしました。

「ハカ」・・・ニュージーランドでの懇親会
さて、日本の伝統的な踊りって、何があるでしょうか?
盆踊りの原型になった「踊念仏」というのがあります。念仏を唱えながら鉦(かね)や太鼓を叩いて踊るという儀式で、平安時代の高僧、空也上人が、念仏を人々に広めるために始めたものです。
踊りは時代とともに変化してきたでしょうが、日本国民の誰もが知っていて、古来から伝わる日本の伝統的文化をいえる踊りはありません。どうしたものかと思案していたところ、
「ロックソーラン」がいいだろうということになりました。
「ロックソーラン」は、北海道に伝統的に伝わる民謡『ソーラン節』を民謡歌手、伊藤多喜雄さんがロック調にアレンジしたものです。日本一荒れているといわれた稚内市南中学校の生徒が、1993(平成5)年、第10回全国民謡民舞大会で日本一になったことから、「南中ソーラン」として知られています。この実話を、斎藤耕一監督が、安達祐実やガッツ石松らを出演させて、「稚内発 『学び座』 (ソーランの歌が聞こえる。)」という映画で発信しています。
その前年、1992(平成4)年、札幌市において第1回「YOSAKOIソーラン祭り」が開催され、その成功のノウハウをもとに「YOSAKOI」は、2000年代にかけて各地に広がっています。
また、1979年~2011年にかけて放映されたTBS系のテレビドラマ3年B組「金八先生」の第5シリーズでも、「南中ソーラン」が踊られた1999(平成11)年からソーランは爆発的に全国に広まっていきました。
小中学校の体育会や運動会のマスゲームとして取り入れられていることも多く、今や国民の踊りといえるだろうということで、私たちは「難中ソーラン」を練習し、懇親会で披露することにしたのでした。

「南中ソーラン」・・・ニュージーランドでの懇親会
ニュージーランド研修後、私も体育会で「南中ソーラン」を積極的に取り入れるようにしました。特にA中学校では、兵庫県内各地のよさこい祭りで活躍していた網干の「純大恋」というよさこいチームにお願いし、南中ソーランを指導しに来てもらいました。「純大恋」の踊る南中ソーランは一味違っていて、動きが大変きびきびしていました。それを少しアレンジして、「A中ソーラン」として根付かせました。

A中ソーラン

5.いじめ問題への取組
ワイタンギ条約を締結し、原住民のマオリ族との共生社会を築き上げてきたニュージーランドでは、いじめ問題は皆無といっていいほどありませんでした。ニュージーランド海外視察で、私が最も感動したのが、生徒たちが非常に仲がいいということでした。
どの生徒たちに質問しても、一番楽しいのは、「家族と一緒にいる時」で、学校で一番悲しいと思うことは「周りの友人が悲しんでいる姿を見た時」と答えるのです。
国技がラグビーであるのに、生徒たちは無用なトラブルを避けるため、不必要な身体接触を禁止しています。手を繋いで歩くことはあっても、挨拶代わりに肩を叩いたり、頭を撫ぜたりすることはありません。
ニュージーランドの生徒たちにいじめ問題が皆無なのは、マオリ族との共生社会を築きあげてきた人為的な文化の成果だと感じました。
今や日本では、子どものいじめ問題は大きな社会問題となっており、大人もハラスメントや虐待などの問題が増加しています。いじめ指導は学校教育の中で最も力を入れてやらなければならないことだと思います。
ニュージーランドの海外視察の後、以下のように、「いじめの土壌」を排除するための方策を練るようにしました。
(1)禁止事項・禁句の設定
①好きな者同士や出身小学校別のグループ化
②デジタル(両価性)思考
③他罰的思考
④生徒同士の身体接触
⑤あだ名や呼び捨て
⑥「3D言葉(でも、だって、どうせ)」
(2)日常生活での生徒指導
①言葉遣いの指導
②あいさつの指導
(3)共生意識を高め、豊かな人間関係を構築するために重視した具体的行動
①あいさつ運動の実施
②友達関係の意識改革
「友を持つ(to have)」ではなく、「友と共にある(to be)」の姿勢で友人関係を築く。
③礼儀作法の指導
(4)いじめ撲滅のためのキャンペーン
①いじめ防止スローガン募集
②人権作文集の作成
③夏休み課題「心のポスター」の作成
④保護司協会「社会を明るくする運動の作文コンテスト」への応募
⑤地域のボランティア活動への参加
(5)保護者の再教育と担任教師の研修
①親への教育
家庭教育のパンフを配布したり、ホームページを利用し、保護者への啓蒙活動を実施。
②頻繁な家庭訪問
③授業参観や学級懇談会の機会の有効利用
④学級通信や学年だよりの定期的な発行義務
⑤通知表所見や個別保護者会での共通理解

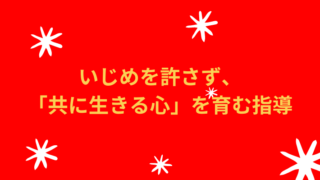
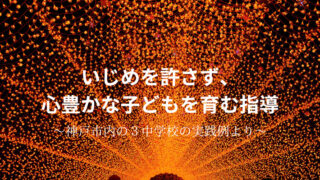
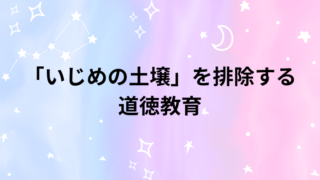
先生を海外研修へ
教師は、幅広い教養を身につけなければなりません。
教育公務員特例法第21条に、
「教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。」
同法第22条に、
「教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。」
という法的根拠が明記されています。
人は、旅をすることで、価値観が変わります。教師の海外研修は非常に効果が高く、意義があると思います。
ぜひ、多くの教師に海外研修を受ける機会を与えて欲しいと願います。
 |
「皆さん、おはようございます」授業では教えない“生き方”教育 スライドで語る全校朝礼のお話/長井功【1000円以上送料無料】 価格:1280円 |
![]()
 |
「皆さん、おはようございます」授業では教えない“生き方”教育 スライドで語る全校朝礼のお話【電子書籍】[ 長井功 ] 価格:1000円 |
![]()
 |
「皆さん、こんにちは」パワースポットが語ってくれた“人生の生き方”/長井功【3000円以上送料無料】 価格:1540円 |
![]()
まとめ
私は、ニュージーランド海外研修(教育視察)で、教育観が大きく変わりました。「共に生きる」という言葉を教育信条にし、共生教育に力を入れるようになりました。そして、スキー実習、修学旅行、国際理解教育、 体育会マスゲーム、いじめ問題への取組等に影響を与えました。
教師は、幅広い教養を身につけなければなりません。教師の海外研修は非常に効果が高く、意義があると思います。ぜひ、多くの教師に海外研修を受ける機会を与えて欲しいと願います。